| 就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||||||||||||||||||
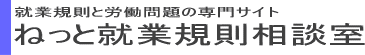 |
|||||||||||||||||||||||||||
| トップページ > |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■雇用保険(失業保険)の加入漏れを防ぐ | |||||||||||||||||||||||||||
従業員が退職した後でトラブルになるケースとして、雇用保険(失業保険)の未加入の問題があります。 パートやアルバイトの場合は、社長が「雇用保険(失業保険)に加入しなくてもよい」と思っているケースが多く、一般の社員の場合は、加入漏れ(資格取得届の提出忘れ)が多いようです。 しかし、雇用保険(失業保険)に加入していない従業員を解雇した場合に、解雇された元従業員が、労働組合や社労士・弁護士などに相談に行くと、間違いなく「雇用保険(失業保険)の加入してもらうよう要求できます。」とアドバイスされます。 雇用保険(失業保険)は最高2年前まで遡って加入することができますので、元従業員が公共職業安定所(ハローワーク)に行って請求すると公共職業安定所から会社に問い合わせがあり、遡って加入させるように指導されます。 そして、失業給付をうけることができる日数は、雇用されていた期間によって変わってきますので、2年以上雇用していた従業員については、採用時から加入していたら本来貰えるはずの日数と実際に貰えることになった日数の差額分の金額を要求してくる場合がほとんどです。 また、労働者の権利意識の高まりから、「働いているときは言いにくい」ので黙っていたパートやアルバイトまで、「辞めたあとは関係ない」とばかりに雇用保険(失業保険)の加入を請求してきたりします。 ※未払い残業代の請求はこのパターンが多いです。
原則として労働者を1人でも雇用している事業は、業種及び規模に関係なく、雇用保険(失業保険)の適用事業所となります。 ※ただし農林水産の事業に関しては、当分のあいだ任意適用事業とされています。 そして適用事業に雇用されている人は、適用除外に該当する場合を除き、事業主や被保険者の意思に関係なく被保険者になります。 被保険者の具体例
公共職業安定所(ハローワーク)に行って、自分の会社の「適用事業所被保険者台帳」を出してもらい、加入漏れと喪失漏れがないかチェックします。 自分の会社は大丈夫と思っていても万が一のことがありますので、是非一度チェックすることをおすすめします。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| →トップページにもどる | |||||||||||||||||||||||||||
| 労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||