| 就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||
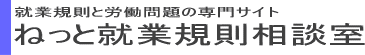 |
|||||||||||
| トップページ > |
|||||||||||
| ■有給休暇の計画的付与について | |||||||||||
有給休暇に関する質問で、「従業員が退職するときに残りの有給休暇を全部請求し、退職日まで出勤しないので、引き継ぎができずに困っている。」とよく相談されます。 私は「有給休暇は、労働者の権利として法律上付与されたものなので、請求された場合は断ることはできません。一応、使用者側の権利として時季変更権(やむを得ない事由がある場合には、請求された時季を変更することができる権利)がありますが、退職日後にまで時季変更権を行使できませんので、有給休暇を与えるしかありません。」と回答しています。→個人的には、不合理だと思いますが、法律論で回答するとこうなってしまいます。 退職時にまとめて請求されてしまった場合は与えるほかありませんので、会社側の予防策としては、有給休暇の取得を奨励し、残日数を少なくする方法で対処するのがいいと思います。 具体的には、年次有給休暇の計画的付与を行います。
有給休暇のうち5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にすることができます。 なお、有給休暇のうち5日については、従業員が病気になった場合などの私的理由で利用できるようにするために残しておく必要があります。 よって有給休暇の日数が10日の人の場合は5日分、20日の人の場合は15日分について計画的付与の対象とすることができます。 ※前年度繰越し分の有給休暇がある人の場合は、繰越し分を含めて5日を超える日数分を計画的付与の対象とすることができます。
計画的付与には、次のような方法があります。会社の実態にあった方法で導入することが可能です。
有給休暇の計画的付与制度の導入するためには、次の手続きを行います。 1.就業規則に計画的付与について規定します。 就業規則に「年次有給休暇のうち5日を超える日数については、労働者の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その協定に定める時季に計画的に取得させることとする。」と規定しておきます。 2.労使協定を締結します。 計画的付与を導入する場合には、就業規則の規定に基づいて労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と次の事項について労使協定を締結します。 なお、この労使協定は労働基準監督署長に届出する必要はありません。 労使協定で定める項目
計画的付与を行った場合は、この有給休暇について労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できなくなります。 計画的付与の日が到来するまでに退職する予定の者が、有給休暇を請求した場合には、使用者はこれを拒否することができません。 有給休暇がない労働者や計画的付与された日数分より少ない日数しかない労働者については、「特別の休暇を与える」、「付与日数を増やす」等の措置をとる必要があります。 なお、特別な措置をとらずに労働者を休業させる場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならなくなります。 |
|||||||||||
| →トップページにもどる | |||||||||||
| 労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||
| Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||