| 労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||||||||||||||||||||
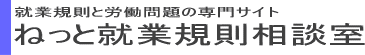 |
|||||||||||||||||||||||||||
| トップページ > 労働基準法の豆知識 > |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■労働契約の内容 | |||||||||||||||||||||||||||
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 労働者は、明示された労働条件が事実と相違する場合には、即時に労働契約を解除することができます。 そして、明示された労働条件が事実と相違することにより労働契約を解除した労働者が、就業のために住居を変更しており、かつ契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。 なお、もし労働条件の明示がなかった場合でも、労働契約自体は口頭で成立するために無効になるわけではありません。ただし使用者に対して罰則(30万円以下の罰金)があります。 ■労働条件の明示事項
■労働条件の明示方法 1.絶対的明示事項 書面を交付(昇給に関する事項は除く)しなければなりません。 2.相対的明示事項 口頭又は書面で行わなければなりません。(口頭でも問題なし。) (参考) 派遣元の派遣労働者に対する労働条件の明示については、派遣元が義務を負わない労働時間や休憩時間等も含めて明示しなければなりません。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 この規定は、例えば「労働者が自己都合退職した場合は違約金として10万円を支払う」といった定めをすることにより労働者の自由な意思決定を不当に拘束したり、また「仕事でミスした場合には1回につき千円支払う」といった損害賠償額をあらかじめ予定するような定めをすることを禁止しています。 (参考)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。 この規定は、例えば労働者が個人的な理由でまとまったお金が必要になり、使用者にそのお金を借りた場合に、「返済は毎月の給料から1万円づつ天引きし、返済が完了するまでは会社を退職してはならない。」というような定めをし、金銭貸借関係により労働者の身分的拘束をすることを禁止しています。 なお、この規定は前借金そのものを禁止しているのではなく、使用者側からの一方的な賃金と前借金との相殺を禁止しているものです。 よって相殺が労働者の自由意思に基づくものである場合には、この規定は適用されません。 (参考)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。 この規定は、労働契約を締結するにあたって、使用者が指定する銀行等と貯蓄の契約を強制したり、使用者が貯蓄金を管理する契約を強制することを禁止しています。 これは、例えば「自己都合退職した時は、貯蓄金を返してもらえるだろうか?」などと労働者を不安にさせたりして、退職を考えている労働者の自由意思を不当に拘束する場合や会社の経営状態が悪化した場合などでは、貯蓄金を労働者に返還できなくなる恐れがあるためです。 なお、使用者による強制貯蓄は禁止されていますが、労働者の委託によって使用者が貯蓄金を管理することは一定の条件のもとに認められています。 (参考) ■労働者の委託による貯蓄金の管理 労働者の委託による貯蓄金の管理には次の場合があります。
■労働者の委託による貯蓄金の管理が認められる条件 1.労使協定の締結と届出について 使用者は労働者の委託により、貯蓄金の管理を行う場合には、労使協定を結び労働基準監督署に届出をする必要があります。(法18条第2項) なお、社内預金による貯蓄金の管理の場合には次の事項を労使協定に定めなければなりません。(施行規則第5条の2)
※労使協定とは? 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます。 2.貯蓄金管理規程について 使用者は労働者の委託により、貯蓄金の管理を行う場合には、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるために作業場に備え付ける等の措置をとらなければなりません。(法第18条第3項) 3.利子について 使用者は労働者の委託により、貯蓄金の管理を行う場合に、その貯蓄金の管理が社内預金である場合には、最低でも年5厘(年0.5%)の利子をつけなければなりません。(法第18条第4項) 4.貯蓄金の返還について 使用者は労働者の委託により、貯蓄金の管理を行う場合に、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければなりません。 (法第18条第5項) 5.貯蓄金の中止命令について 使用者が、労働者の貯蓄金返還請求に応じない場合に、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、労働基準監督署長は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止することを命ずることができます。(法第18条第6項) 6.中止命令があった場合の措置 労働基準監督署長に貯蓄金の管理を中止することを命じられた使用者は、遅滞なく、管理している貯蓄金を労働者に返還しなければなりません。(法第18条第7項) 7.報告義務について 貯蓄金の管理が社内預金である場合には、使用者は、毎年3月31日以前1年間の預金管理の状況を、4月30日までに、労働基準監督署長に報告しなければなりません。(施行規則第57条第3項) |
|||||||||||||||||||||||||||
| →労働基準法の豆知識にもどる | |||||||||||||||||||||||||||
| 労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||