| 育児介護休業法の基礎知識について解説 | ||||||||||
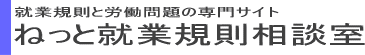 |
||||||||||
| トップページ > 育児介護休業法の豆知識 > |
||||||||||
| ■子の看護休暇 | ||||||||||
小学校に入学する前の子を養育する労働者は、次の事項を明らかにして事業主に申し出ることにより、負傷又は疾病にかかった、その子の世話をおこなうための休暇(子の看護休暇)を取得することができます。 なお、子の看護休暇は、年度間(4月から翌年3月まで)に5労働日が限度となっています。 子の看護休暇の申出事項
※事業主は、「対象となる子が負傷又は疾病にかかっている事実」について、申出者に対してその事実を証明する書類の提出をするように求めることができます。
■事業主の義務 労働者から、子の看護休暇の申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができません。 ただし、労使協定で子の看護休暇を取得することができない労働者として定めた場合には、その労働者からの子の看護休暇の申出を拒むことは可能です。 ※労使協定とは? 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます。 ■労使協定により子の看護休暇の対象から除外できる労働者 次に該当する場合については、労使協定を締結することにより、子の看護休暇の申出ができない者として定めることができます。
※育児休業の場合と異なり、配偶者が常態として子の養育することができる労働者の場合であっても子の看護休暇の対象外として労使協定で定めることはできません。
事業主は、労働者が子の看護休暇の申出をしたこと、又は取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 なお、解雇その他不利益な取扱いとなる行為とは、の看護休暇の申出又は取得したこととの間に因果関係がある行為で、次のような場合が該当します。 (解雇その他不利益な取扱いの例)
|
||||||||||
| →育児介護休業法の豆知識にもどる | ||||||||||
| 労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
||||||||||
| Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | ||||||||||